【知らないと後悔する】ハイロックスジム専門クラスを受けてわかった5つのこと
クロスフィット経験あり
でも、そこまで身体能力の自信がないクロスフィットジムでは平均以下の筆者が
実際にジムでハイロックスクラスを受けてみてわかったことをご紹介します。
最初に結論としてわかったことは
「多分このままハイロックスレースに参加すると惨敗するし、リタイヤするかもしれない」
「でも事前に準備しておけば、初心者の私でもなんとかなるかもしれない」
ということ。
ハイロックスジムに興味がある方、横浜で開催されるハイロックスレースに参加を検討されている方の参考になれば幸いです。
※あくまでも運動好きレベルの個人の感想なので、ハイロックスやクロスフィットのプロアスリートの方には参考にならないかもしれません。でも、一般の方には参考になると思います!
①ランナー専門の人は間違いなくワークアウトで苦戦する
ハイロックスは8kmのランニングと8種類のファンクショナルムーブメントから構成される合計タイムスコアを競うレースです。
よって圧倒的にランニングが得意な人にはアドバンテージがあるスポーツです。
しかし、ランニングが得意な人、つまりランナーの人の多くは
走ることに最適化された体を持っているため、重いウェイトを扱うファンクショナルムーブメントで間違いなく苦戦すると思われます。
私もランニングはそこそこ走れるのですが、実際にハイロックスクラスをやってみて次のような感想を持ちました。
・スレッドプルが押せない(男性オープン152kg)
・7種目目のサンドバックランジは疲れた体には地獄(男性オープン20kg)
かつ、落としてしまったらペナルティや失格あり
・最終種目ウォールボールは手も足も動かないかも(男性オープン6kg)
ローイング、スキーなど漕げばなんとかなる競技なら時間をかければクリアできるものの、ウェイトがある競技はランナー専門の人はかなりハードルが高いと思います。
重いウェイトがどうしても無理なら、ハイロックスのエントリーカテゴリーのうち「チームリレー」がお勧めです。チームリレーなら8種類のワークアウトのうち2種目を選んで参加できます。
②ワークアウトはスキルの有無で差がつく
ハイロックスには8種類のワークアウト(ファンクショナルムーブメント)があります。
スキーエルゴ 1000m
スレッドプッシュ 50m
スレッドプル 50m
バーピーブロードジャンプ
ローイング 1000m
ファーマーズキャリー 200m
サンドバッグランジ 100m
ウォールボール 100回
これらワークアウトは
「時間をかければクリアできるもの」
「体力や筋肉量に依存するもの」
といった種目もあるため、圧倒的な筋肉、持久力があればなんとかなってしまう場合もあります。
でも、一部、スキル(技術)の有無によって大きな差が出てしまう競技があります。
それが次の3つの種目です。
スキーエルゴ、ローイング
フォーム、動作によって距離の進み方が全然違う。無駄な動きをしないことで体力の消耗を抑えられる。
引き方、パワーの配分など、さまざまなテクニックを身につけることでスコアが上がる種目です。
ウォールボール
ボールの持ち方、受け止め方、足と手の動きなど・・・効率的な動作を身につけることでスコアを上げることができる。
ハイロックスの場合、最終競技になるため、スキルの有無にによって、ここで大幅にタイムロスしてしまう人も出てきそう。
とはいえ、ランニングが得意なら、スキルがなくてもランで圧倒的に時間を稼ぐこともできます。
でも、これらスキルで解決できる競技は、できるだけ事前に練習して、やり方、動きを身につけておきたいところです。
③ウェイトに慣れてレース全体を経験しないとダメ
私は「個人オープン」カテゴリーの参戦を検討中です。
実際に「個人オープン」の場合、次の競技をやらなければなりません。
ランニング 1km
スキーエルゴ 1000m
ランニング 1km
スレッドプッシュ 50m (152kg)
ランニング 1km
スレッドプル 50m(103kg)
ランニング 1km
バーピーブロードジャンプ 80m
ランニング 1km
ローイング 1000m
ランニング 1km
ファーマーズキャリー 200m(24kg×2)
ランニング 1km
サンドバッグランジ 100m(20kg)
ランニング 1km
ウォールボール 100回(6kg)
ここでのポイントは2つあります。
・各ワークアウトのウェイトは事前に経験しておかなければ絶対にマズイ
・全16項目を通しで模擬レースをやらないと負荷がわからないし慣れないのでヤバイ
正直な意見として、ハイロックスのワークアウト単体は、クロスフィットをやっている人からすると、大した重さではないので単体だけ見るとなんとかなります。
でも私のようにクロスフィットをやっていても平均以下の一般人からすると結構な重さがあるので、事前にこれら重さに慣れておかないとハイロックスの大会では話にならないと思いました。
その上で問題なのは、これら全16項目を通してレース全体の負荷を経験しておく必要があるという点です。
クロスフィットのクラスでもランとワークアウトの複合メニューが頻繁に登場しますが
ランとワークアウトの複合メニューは、それ単体を永遠に繰り返すのと比べて別世界の辛さがあります。
ハイロックスの場合、私のような一般人の場合、レース時間は1時間半以上はかかると思われるため、それだけの時間、動き続ける負荷に慣れるためには
ハイロックスレースの本番シミュレーションを繰り返し体験しておく必要があると思いました。
④ランニングでタイムの差がつく
実際にハイロックスクラスをやってみてわかったこと
それは、クロスフィットなどをやっている人の中ではハイロックスは
・ワークアウトではタイムの差がつきにくい
・でもランニングでタイム差が大きくつく
という点です。
重いウェイトを扱える人の多くは体が大きく、パワーもあります。
でも、そのような人の多くはランニングがあまり速くありません。(一部例外の人もいますが)
よって私のようなパワーがない人にとってはランニングがタイムで貯金を作る上で重要なポイントになりそうです。
これはレースの後半に行くほど、差が出てくると思いました。
⑤サンドバックランジで失格になるリスクあり
ワークアウト7番目(最後から2番目)にあるサンドバックランジは持久力、パワーがない人にとっては落とし穴になる競技だと思いました。
なぜなら、男性のオープンの場合は20kgのサンドバックをかついで100mランジしなければならないからです。(女性の場合は10kg)
クロスフィットジムでは平均以下の私でも20kgのサンドバックを担いでランジすることは全然可能です。でも、100mランジできるか?というと単体ワークアウトとしてみても怪しい部分があります。
ランや他のワークアウトで疲れ切った状態、多分競技開始から1時間半くらいの時点で、サンドバックランジをやることになります。
しかも、このサンドバックランジはペナルティがあります。
1回落とすと5m戻される
2回落とすと10m戻される
3回落とすと即失格
サンドバックを落とすとダメなのです。
なので途中で疲れたら、サンドバックを抱えた状態で立って休憩するしか方法がありません。
そして、ちょっと考えてみてください。
「1回落としただけなら5m戻されるなら、まだ大丈夫だよね?」
と思うかもしれませんが、1回落とすということは2回落とす可能性は極めて高いということになります。なぜなら5m戻されるからです。
100mゴール直前に落とすならまだ大丈夫かもしれませんが
50mくらいで落としたら・・・・1回目だとして限りなく失格になる可能性が高い
と思われます。
ここで失格になったら、これまでのレースは全て無駄になります。
ハイロックスには8種類のワークアウトがありますが、唯一、失格があるのはサンドバックランジです。
まとめ
実際にハイロッククラスを受けてみてわかった5つのことについて解説しました。
これからハイロックスの大会に参加する人は、各ファンクショナルワークアウトについて一度、ウェイトややり方について経験しておくことをお勧めします。
当日、ぶっつけ本番では全然歯が立たず、リタイヤしてしまうと悲しいですし、チームリレーの場合はチームメンバーにも迷惑をかけてしまうかもしれません。
ハイロックスのファンクショナルムーブメントを教えてくれるジムも続々登場していますので、ぜひチェックしておきましょう。


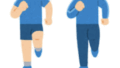

週間人気記事ランキング